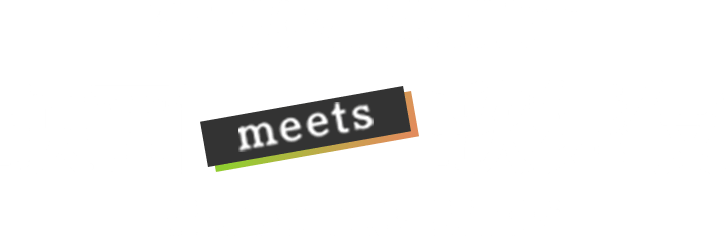尾上松之助―日本最古の映画スター“目玉の松ちゃん”のすべて
講演採録
「尾上松之助生誕130周年記念講演・特別上映会」講演採録
歌舞伎役者としての尾上松之助
児玉竜一(日本女子大学文学部助教授*)
「歌舞伎役者としての尾上松之助」という、一見分かりにくい表題を掲げましたが、冨田先生のお話や、とりわけ小松先生の「映画俳優 尾上松之助」という題と対になるつもりでつけました。この題で示そうとしたポイントは2つあります。一つは、この「尾上松之助」という名跡です。歌舞伎では名前のことを名跡と言いますが、この名跡を名乗った人は、“目玉の松ちゃん”一人ではありませんので、この名跡が含む意味を歌舞伎の歴史の中から説明いたします。もう一つは、その名跡を踏まえて、本日の主人公である“目玉の松ちゃん”の、いわば体の中に流れる歌舞伎の技術、大きくいうと歌舞伎の伝統が松之助映画の中にどのように現れるのかを、本日の映画[注1]に即して例を挙げます。私は歌舞伎の研究者で、歌舞伎と映画とは密接な関係があると信じているのですが、どうも歌舞伎研究者で映画を研究しようという人間は少ないので、いわば「鳥なき里のこうもり」ですが、歌舞伎研究の側からという立場で主にお話しいたします。
まず、尾上松之助という名跡についてです。この名跡を彼が継いだことについては彼の自伝で語られています。この自伝は大正6(1917)年12月の本ですが、引用は、岡山県で出ている岡山文庫という叢書で最近復刻された『目玉の松ちゃん 尾上松之助の世界』からのものです。その中に、「三十六(編註:明治36[1903]年)年一月には長崎祇園座に出勤して後引続き九州巡業していた。丁度、ちょうどその年の十二月小倉で開演中、今は故人の当時の太夫元の港富右衛門氏と、尾上和若氏と私の三人で宿の一室に寄りあった事があった。何分極月の寒さを、火鉢囲んで話すのだから、話はそれからそれへと果てしもなく続いたが、ふと富右衛門氏が、『音羽屋さん、あなた一つ襲名してはどうですか』と突然の話」[注2]とあります。
「音羽屋」というのは屋号です。歌舞伎役者には屋号がありますから、尾上松之助にもありました。同時に歌舞伎役者は俳名を持っておりまして、例えば市川団十郎は「三升(さんじょう)」といいます。同じように、尾上松之助も歌舞伎の伝統の中に生きた人の常として、どんな俳句を詠んだかまでは知りませんが、映画俳優としては珍しくも俳名を持っているのです。多分、後になってつけたのでしょうが「目玉」といいます。
で、自伝の続きですが、「『はあ、そりゃしてもよろしいが一体誰れの名の襲名するのです』『この和若さんの師匠の和市さんの前名尾上松之助なのです。あなたがその二代目を襲名なすってはいかがです』と言うと和若氏も『そりゃ、全くよい思いつきです。松之助と言えば、尾上多見蔵の孫の名なんだから、それに私の師匠の前名ですから是非一つ襲名して欲しいものですな』としきりに勧められた。私も大分思案に暮れたが心も動きかけていた」[注3]というわけで、その翌年に襲名することになっています。
この「松之助」という名跡について、同じ本の別のところに「松之助とは、富右衛門氏の言ったように明治劇壇では、有名な古今無類と賞されていた尾上多見蔵氏の孫の名で、尾上和市なる人の前名で、私が二代目となったのである」[注4]と書かれております。この尾上多見蔵ないし尾上和市という名前については、『都新聞』の記者かつ演劇研究者、そして大衆小説作家だった伊原青々園という人の『明治演劇史』(昭和8[1933]年11月、早稲田大学出版部)に記述があります。そこには「多見蔵の次男は、母が市川鰕十郎の娘なので、市川市蔵といひ、有望の人であつたが、慶応元年三月二日、三十三歳で没した。長男、尾上和市も弟が死んでから人気を高め、後に璃寛となった嵐和三郎や澤村訥升よりも上の地位に居たが、慢心して同業者と折合はず、父とも不和となつた上に発狂して、明治十一年十月廿二日に四十七歳で歿した。また、外孫を千太郎といひ、若立役も女方も兼ねたがあまり振はなかつた。たゞ門人の多見之助がやゝ頭角を顕し、大正になつて多見蔵の名を嗣いだが、これも長生しなかつた」[注5]と書かれています。
この尾上多見蔵という人は、歌舞伎でもそんなに取り上げられる名前ではありませんが、映画に馴染みのあるところですと溝口健二監督の『残菊物語』(1939年)、後にも長谷川一夫や市川猿之助の主演でリメイクされましたが、あの映画の中で主人公の尾上菊之助(花柳章太郎が演じています)が東京の劇壇から大阪へ落ちる。その時、私が引き取るんだから大船に乗った気でいろ、と言う大阪の大立者がおります。あれが尾上多見蔵で、菊之助が大阪へ行ったときには既に亡くなっていましたので、多見蔵を頼ったというのは小説および映画のフィクションなのですが、幕末から明治にかけての大阪劇壇きってのトップ役者です。この人は寛政10(1798)年の生まれで、明治19(1886)年に88歳か89歳で亡くなりましたから、当時としては大変な長生きで、写真が残っている役者の中で恐らく生まれが最も古い人でしょう。
国立劇場が編纂した資料集『歌舞伎俳優名跡便覧』で尾上多見蔵の項目を引いてみますと、彼には瀬川和市といういつ頃名乗っていたか分からない名前があり、中村和市とも名乗り、やがて文政3年から尾上多見蔵となり、嘉永元年に大川八蔵、それからまた尾上多見蔵に戻るという経歴をたどりました[注6]。ですから、尾上多見蔵家は「和市」という名前に縁があることは間違いありませんが、息子の和市に子どもがいたという話は聞かない。というのは、この和市は、発狂したということでは有名ですが、伝わっているエピソードも多くないからです。
では、尾上松之助という名跡を他の誰かが名乗ったことはないのか。この『歌舞伎俳優名跡便覧』は、そういうことを一覧できる便利な本です。
そこで、三代目の三桝稲丸(安政5年~明治34年)という役者が、尾上松之助を名乗ったことがあるという記録があります。尾上亀三郎という名前から明治4(1871)年頃に尾上松之助と名乗った、と『名跡便覧』にあります[注7]が、 調べますと明治2(1869)年1月に角座で尾上松之助という役者が座元をやっております。座元というと年配の偉い人がやるのかと思いますが、大阪には子どもに座元をやらせる伝統がありました。ですからこの時点では子どもかもしれませんが、とにかく明治2年にすでに尾上松之助を名乗る人がいたのです。それが明治4年からの松之助と同一人物かどうかは、わかりません。明治4年からの方は、明治7年に実川百々之助という名前になり、その後三代目三桝稲丸となる。この人は、特に歌舞伎史上に名を残した人ではありません。
さらに、この人が実川百々之助を名乗っている同じ時代、明治7(1874)年や明治9(1876)年ごろから、明治20年代まで、別の役者だと思いますが尾上松之助という人がいるのです。番付が残っています。ですから、“目玉の松ちゃん”の前に少なくとも2人の尾上松之助を名乗った役者がいたことは確実です。そして、この2人の他に尾上松之助という名前の人がいたかどうかまでは、確実には分かりません。
[講演者注]講演後、『歌舞伎俳優名跡便覧』の大幅に増補された新版が出ました。それによると、多見蔵の三男に尾上梅朝という人がいて、その息子が二代目尾上和市を名乗っています。そして、この人が明治25年11月まで名乗っていた前名が「尾上松之助」。ですから、自伝にいうところの「多見蔵の孫の前名」は、これを指すようです[注8]。しかし、「尾上松之助」を名乗ったのが、この人だけではなかったことは変わりがありません。
というのも、この名跡は、歴史的に非常に筋目のいい字面の、ありうべき名前だからです。尾上家にとって、この「松」という文字は大変重要な文字です。初めて尾上松助(のちに松緑)という名跡を名乗ったのは、18世紀から19世紀に変わる頃の名優ですが、その子が三代目尾上菊五郎、その孫が五代目尾上菊五郎、その息子が昭和の名優・六代目尾上菊五郎、小津安二郎が『鏡獅子』(1936年)を撮ったあの六代目というわけで、尾上菊五郎家のいわば中興の祖に当たるのが初代尾上松助(松緑)という人です。その「松」という文字ですから、これは尾上家にとって大事な文字です。「尾上の松」という、歌によまれた高砂の松に通じるところもあります。
ですから、尾上松之助というのは尾上一門の直系といいますか、一門の大事な名前をいただいたことを鮮明にした、一門の中でも良い名前です。歌舞伎から映画に入った人にはこういうことが沢山ありまして、例えば、片岡千恵蔵の「千」という字がそうです。片岡家というのは屋号松島屋なので、常緑樹を象徴する千代あるいは千代之助という名跡を持っております。「千」という字は片岡家にとって大事な文字です。嵐寛寿郎にも、璃寛という嵐家のいちばん大事な名前に使われた「寛」の字があります。そうした名前の継ぎ方をしますから、歌舞伎役者は名前の上にも痕跡をとどめているのです。
目玉の松ちゃんの尾上松之助が自伝で語っているように、二代目として継いだのか、どうかは分かりません。しかし、歌舞伎役者の芸談にさんざん付き合った者から申しますと、自伝の細部が間違っているのは当然です。全部正しい自伝などほとんどないと言っていいほど、今も昔も芸能者自身が語る自伝とはあやふやなものです。その点について、神戸の郷土史家の三船清先生も、『岩波講座 日本映画』の中で、松之助の自伝にはいろいろと疑惑があると言っておられます[注9]。特に歌舞伎俳優の代数というのはいい加減なものです。いちばん近い例が市川雷蔵です。雷蔵は名跡を継いだ時は七代目なのですね。それはその月の演劇雑誌『幕間』にも自身そう語っております。ところが、もう一人いたことが分かったらしく、その後、特に断りもなしにいつの間にか八代目になりました。今では八代目が通り相場ですが、継いだ時は確かに七代目でした。
歌舞伎役者の名跡とはそれぐらい動くものですから、松之助が二代目を名乗る前に2人いようが3人いようが、歌舞伎の方からすれば実は大きな問題ではなくて、要するに歌舞伎役者の代数とはそんなに厳密なものではないと覚えていただいてよろしいと思います。
しかし、こう申しますと、尾上松之助が何人いたかも分からないのか、歌舞伎の研究とはそんなに進んでいないのかと言われそうですが、先ほど来、歌舞伎、歌舞伎と申していますが、現在私たちが「歌舞伎」と考えている、歌舞伎座や国立劇場で上演しているものだけでなく、“目玉の松ちゃん”が登場しようかという時代には、歌舞伎という言葉が含むキャパシティが大変広かったのです。
それを象徴的に示すために用意したのが、明治41(1908)年の「大日本帝国俳優一覧」というプリントです[図1]。たくさんの役者の名前が並んでおりますが、この中でいわゆる大歌舞伎の役者は1割あるかないかぐらいです。例えば尾上松之助の名前を探しますと、全体の中ではかなりいいところにいるのですね。明治41年は、彼が映画界に入る直前です。例えばその隣にいる尾上幸十郎という人ですが、あまり聞いたことがありません。市川九蔵、この人は大歌舞伎の人ですが、その隣の中村七賀之助というのでしょうか。あるいは市川猿十郎だとか市川団右衛門、この辺になると大歌舞伎の脇役です。
図1:大日本帝國俳優一覽(明治41[1908]年)
その下の、二段目以降の役者たちは、当時の言葉でいう小芝居あるいは旅芝居の役者です。歌舞伎と一口に言っても、大別すると大芝居つまり一流の歌舞伎と、二流の小芝居と、全国を巡演している旅芝居、さらにつけ加えると素人の村芝居の4つがあって、現在、歌舞伎と普通に呼ばれるのは大芝居だけです。これは例えて言いますと、プロ野球もあれば社会人野球や高校野球もあり、近所の草野球もあるのをすべて野球と呼ぶようなものです。この小芝居の役者と大芝居の役者の間には厳然とした差別がありまして、小芝居から大芝居に這い上がる役者もいないわけではありませんが、非常に数が少ない。そして、この小芝居や旅芝居が、明治後半から昭和にかけて、時代劇映画や大衆演劇に形を変えた、というのが私の考えるところです。大衆演劇は、例えば都内では十条の篠原演芸場や浅草の木馬館などでやっていますが、レパートリーは昔から変わらぬ任侠ものだったり、時に新派や新喜劇であったりします。それが、ある年代までは歌舞伎をやっていたと考えていいのだと思います。
近頃は小芝居の研究も進んできましたが、旅芝居のことは今もよく分かりません。というのは、上演資料が少ないからです。ですから、映画に入るまでの尾上松之助は全国のどこを巡演していて、どこの劇場にいつ出たかが分かると素晴らしいと思うのですが、恐らく私どもが生きているうちには実現しないでしょう。各地の図書館に行っても、未整理の資料が書庫の隅に眠っていたりするのではないかと思うのですが、なかなか陽の目が当たりません。ですので、いま分かる限り、あるいは類推される限りの概況としてお話をするしかないのですが、旅芝居と小芝居が明治の末にすでに二流と考えられたのに対し、明治のいわば新国家体制の方針に合わせて、大歌舞伎はどんどん高尚化してゆきます。ですから時代劇映画は、そこからこぼれ落ちたレパートリーをたくさん持っています。映画会に参入してくる役者たちが、それを演じていたからです。その代表的なものが講談ダネや浪曲ダネであったり、敵討ちものだったりするのです。
これから上映される『渋川伴五郎』[注10]は、敵討ちものでかつ武勇ものです。分類の名称は確定的なものではありませんが、歌舞伎の方から申しますと、これらは幕末の大阪辺りで流行した芝居の匂いがします。あるいは第2部で上映される『豪傑児雷也』は忍術もので、「エイッ」と言って姿がスッと消えるのは映画ならではですが、歌舞伎でも、「エイッ」と言ってセリ下がれば、あるいは田楽返しを使えば、姿は消したことになります。忍術ものとか、術を使う武勇ものは幕末の大阪でたくさん上演されましたが、『児雷也』は江戸でも大流行した芝居ですから、これは歌舞伎直系のレパートリーと言うことができます。
それでは、この後に上映される『忠臣蔵』をご紹介しましょう。便宜的に場面を書き出してみました[図2]が、『忠臣蔵』は、知られている限り2つの版がございます。これからご覧いただくフィルムセンターの版(NFC版)と、マツダ映画社が持っている版(マツダ版)はちょっと違っています[注11]。フィルムセンター版だけにある場面もありますし、逆にこちらにはない場面も少しあります。この版には浪曲が入っておりますが、これを芸能史的には、「節劇(ふしげき)」と申します。歌舞伎は普通、義太夫節に乗って芝居をする場合が多いですが、それを小芝居や旅回りでは節劇と言い、浪曲に合わせて芝居をします。恐らくその名残で、無声で撮った松之助の映画に後から浪曲を入れたのだと思われます。
図2:『忠臣蔵』場面一覧
例えばシークエンスの15番を見ていただきますと、「山科閑居」の妻子訣別ですが、大石内蔵助のお母さんが出てきます。現在知られている「忠臣蔵」の物語に大石内蔵助の母親が出てくるという話はあまり聞きませんが、講談の中ではさんざん語られています。さらに、その講談を歌舞伎化したお芝居として、明治年間に盛んに上演されているのです。ですから、松之助はその歌舞伎をそっくり映画にしたわけです。映画研究の方で、原作が講談か浪曲かと、分類しておられるのをみますが、講談が基になったか、浪曲が基になったか、あるいはそれを歌舞伎化したものが基になったかは、これは「卵が先かニワトリが先か」よりもさらに見分けがつけがたい。私自身は、講談や浪曲を基にした歌舞伎を映画化したもの、と考えればよいと思っています。
『忠臣蔵』の場合は、様々なエピソードは、そのほとんどが歌舞伎プロパーの台本および、講談や浪曲を基にした歌舞伎に由来しています。フィルムが断片なので分かりにくいですが、例えばシークエンス8番に内匠頭が刃傷した直後に脇坂淡路守というのが出てくるところがあります。「おのおの、静まり召され」と言って、脇坂淡路守が奥にいると、手前から斬られた吉良が逃げてくるところで、シーンは終わっています。これだけでは脇坂淡路守が何のために出てきたか分かりませんが、恐らくその先には、脇坂淡路守と吉良上野介がぶつかって、脇坂淡路守が、大紋に血がついた、脇坂の定紋を汚したと言って吉良に頭をはり倒すシーンがあったはずです。これも講談でよく語られていますし、歌舞伎でも演じられていまして、近いところでは昭和58(1983)年5月に南座で上演されまして、私も見たのですが、「頭張りの忠臣蔵」と通称します。「頭張り」とは脇坂淡路守が頭を張る、叩くという意味です。そんなところも歌舞伎の方から類推されるわけです。
もう一つ、シークエンス16番に「大石東下り」という場面があります(これは、私の見たところでは、フィルムの順番がシークエンスの中で入れ替わっていると思いますので、ちょっとご注意いただきたいと思います)。ここは大石が関東を下ろうとして街道をやってくると、雲助たちに絡まれます。この雲助にご注目いただきたいのですが、よく目を凝らすと、雲助の入れ墨はどうもシャツのようです。入れ墨模様のシャツを着るのは歌舞伎では普通のことです。これと同じことが『渋川伴五郎』にもありまして、相撲のシーンで、「飛入勝手次第」というので敵役の侍が土俵に現れますが、これがどう見てもいわゆる「着肉」(きにく)という、ぬいぐるみのような肉を着ています。相撲取りの役などで肉を着るのも、歌舞伎そのままの習慣です。役名は分からないのですが、松之助が仏壇を背負った相撲取りの役を演じている写真があります[図3]が、一目瞭然、肉を着ています。これは歌舞伎を取り入れたというよりも、当時の役者にとっては、歌舞伎そのままであることこそ自然だったと言うべきでしょう。尾上松之助とはそういう環境の中に生まれ育ち、ジャンルとして未熟だった映画という新世界に入ってきた人だったと言えます。
図3:肉を着た相撲取り役の松之助(左)
さて、『忠臣蔵』に戻っていただきまして、シークエンス18、これは「南部坂雪の別れ」です。残念ながら今からNFC版にはないのですが、瑶泉院のもとに大石内蔵助が暇乞いにやってくる。そして、旅日記だと言って連判状を置いて帰る。ところが、間者がその連判状を盗もうとするので立ち回りになるのですが、マツダ版ではこの立ち回りが庭先で行われます。この庭先にご注目いただきたいのです、と言うのは、この瑶泉院の住む浅野家の下屋敷の庭と、後で出てくる討ち入った先の吉良の庭が同じなのです。雪の形も後ろの建物の形も同じで、これは書き割りを使い回しているとしか考えられません。この辺も、いわば旅芝居的な安価な歌舞伎の発想です。
ただ、歌舞伎にも様々な歴史があります。スペクタクルが流行した時代、あるいはリアルな庶民生活を写実的に描くことが流行った時代、格調高く演じることを旨とした時代、あるいは実録趣味といいますか、講談などで語られた、実際の事件を描こうとした時代、それから時代考証を一生懸命やった時代。「歌舞伎400年」というのは誇張で、普通の劇の形態をとってからは大体300年ですが、その中でたくさんの有為転変があります。ところが、映画はその300年を最後に受け止めて、その有為転変全部を見事になぞるわけです。ですから、本日ご覧いただく尾上松之助という役者が演じる映画のバラエティの豊かさには目を見張られるかと思います。つまり、『忠臣蔵』では、松之助は格調高く大石内蔵助を演じますが、その前に上映される『史劇 楠公訣別』などは『忠臣蔵』以上に格調が高いのです。摂政宮(後の昭和天皇)が観たこともありますが、それ以前に、「史劇」と名乗るわけですから、明治の歴史劇運動の影響を受けた、明治独特のテイストをたたえています。それに比べると『忠臣蔵』は江戸時代以来の感覚の伝統を引きずっています。
それが『豪傑児雷也』となりますと、これは江戸時代以来というより、江戸時代で時間の止まった歌舞伎でして、様々なスペクタクルを見せてくれますが、一部、明治のテイストも入っています。例えば、管領持氏公という人物は、八文字の髭をつけています。江戸時代の人間はあまり髭を生やすことを好みませんし、八文字髭を偉い人と見るのは明治の感覚です。楠公が髭を生やしているのと同じです。それと「エイヤッ」と術を切っている児雷也とが同居しているのは、江戸時代の歌舞伎と明治の歌舞伎の感覚とが同じ画面の中に流れているのです。
呉智英という評論家がおりますが、彼が「漫画の歴史は、近代文学100年の歴史を20数年で駆け抜けた」という言い方をしています。それに倣うと、時代劇映画の歴史は、歌舞伎300年の歴史を大体50年か60年ぐらいで駆け抜けたのだと思います。ですから、それぞれの時代の歌舞伎のテイストにマッチする、それぞれの時代の時代劇があります。格調高いもの、写実的なつもりのもの、実録風を売りにするもの、残酷趣味のもの、わざと時代考証を無視した現代調のもの、そのすべてが歌舞伎で試みられています。松之助映画は、私のような歌舞伎研究者が見ますと、明治40年から大正にかけての、申し訳ないけれども二流の小芝居や旅芝居で演じられていた芝居の感覚や演出を知るための最高の資料でもあるのです。けれども同時に尾上松之助という人は日本最初の大スターですから、そのオーラも感じ取っていただきたいのです。
最後に値段のことをお話しします。明治40(1907)年頃で、歌舞伎座ですと1等席は2円50銭です。そしていちばん安い、役者が豆粒のようにしか見えない3等席が30銭です。しかし映画館だと、尾上松之助のアップが10銭で見られるのだから魅力ですね。しかも、松之助は全国津々浦々に知られるスターとなる。全国規模のスターというのは映画以前には難しいのです。それ以前、歌舞伎役者の大立者も時には旅に出ますが、巡演してくる人間を見ても本物か偽者か分からないという時代でした。二代目市川猿之助が衣笠貞之助と『川中島合戦』(1941年)の撮影で川中島へ行った時に、巡業している偽者の猿之助と鉢合わせしたという話もありますから、そんなに古い話ではありません。しかし映画ができて、全国の人々がスターを共有して、しかもそれを安い値段で満喫できる時代を迎えます。そこが、歌舞伎から映画へと娯楽の王座が移ってゆく大きな要因だったと思います。
- 当日上映された映画作品は以下の通り。(特記のないかぎり、国立映画アーカイブ所蔵作品) 『史劇 楠公訣別』(17分、16fps、35㎜)1921年、日活 『忠臣蔵』[活弁トーキー版](42分、35㎜)1910-12年、横田商会 『忠臣蔵 天の巻 人の巻 地の巻』[部分](20分、16fps、35㎜)1926年、日活 『豪傑児雷也』(21分、16fps、35㎜)1921年、日活 『弥次喜多 善光寺詣りの巻』(61分、18fps、16㎜)1921年、日活(京都府京都文化博物館所蔵) 『渋川伴五郎』(63分、24fps、16㎜)1922年、日活(弁士:澤登翠、伴奏:村井音文)(京都府京都文化博物館所蔵)
- 尾上松之助、中村房吉『岡山文庫 178 目玉の松ちゃん―尾上松之助の世界―』日本文教出版、1995年)80-81頁。
- 同上、81頁。
- 同上、82頁。
- 伊原敏郎(伊原青々園)『明治演劇史』(早稻田大學出版部、1933年)722頁。 (国立国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1226047/1/372
- 国立劇場調査養成部調査記録課編『歌舞伎俳優名跡便覧』[第五次修訂版](日本芸術文化振興会、2020年)135頁。
- 同上、320頁。
- 同上、141頁。なお、同書では二代目尾上和市の家系として「二代目尾上多見蔵の二男、または初代尾上梅朝の息子」とし、参考情報として「三代目三枡稲丸が明治7年1月まで尾上松之助を名のっているので、それ以降に(尾上和市は松之助を)襲名したと思われる」と記している。
- 三船清「活動写真の大スター尾上松之助」、特に「松之助自伝の虚実」の章を参照。『講座日本映画1 日本映画の誕生』(岩波書店、1985年)137-149頁。
- 本講演当日に上映されたフィルムは京都府京都文化博物館所蔵の16㎜プリントだが、その後、2019年度にフィルムセンター(当時)がマツダ映画社より、元素材となる可燃性35㎜染調色プリントから、中間素材となる不燃性35㎜インターネガおよび再染調色された35㎜プリントを購入し、上映企画「発掘された映画たち2022」において(2022年5月)、『𦾔劇 渋川伴五郎 霧島山蜘蛛退治の巻』として公開した。
- マツダ版については、その後、2017年度にフィルムセンター(当時)がマツダ映画社より、元素材となる可燃性35㎜プリントから、中間素材となる不燃性35㎜インターネガとノイズリダクションを施した35㎜音ネガ、およびこれらのネガより作成された35㎜プリントを購入し、上映企画「発掘された映画たち2018」において(2018年2月)、『実録 忠臣蔵』[活弁トーキー版]として公開した。
*肩書はブックレット刊行時(2007年3月)。現職は、早稲田大学文学学術院教授。
“目玉の松ちゃん”の功績
冨田美香(立命館大学文学部助教授*)
私の演題は「“目玉の松ちゃん”の功績」というものですが、先程の児玉先生とは違いまして、私自身が松之助の存在を知ったのは文献資料からですし、彼の出演した映画を初めて見たのは18歳の時でした。そんな人間がこのような場所で話をしていいのかと躊躇はしたのですが、京都でこの5、6年間過ごしていますので、彼を愛して映画スターに育てた「京都」という土地から見た松之助像というものを、皆さまにご紹介したいと思います。お配りした史跡マップ[図1][図2]は、おまけとして、こちらに来る前に新幹線の車中で楽しみながら作ったもので、130年に一度の「松之助祭」でもありますので、お持ち帰りのうえ、京都観光の際はぜひこれをガイドとして「松ちゃん」の足跡をたどっていただければ幸いです。この時間は、「松ちゃん」の足跡をたどりつつ、そこに込められた人々の愛情を感じ取っていただければと思います。
まず、「松之助の功績」と題した以上は、松ちゃんの功績を3点にまとめたいと思います。
一点は、この「松ちゃん」という愛称が示している、伝説的な人気スターのあり方です。東京にいると、尾上松之助といっても文献上の、いわば歴史的な存在になってしまいますが、京都にいるとまだまだ「松ちゃんの葬式見たんや」と言う方もいますし、ダウンタウンの出るテレビ番組を家族で見ていて「松ちゃんといえば“目玉の松ちゃん”や」というおばあちゃんがいて、それで尾上松之助を初めて知ったという学生もいるのです。それだけ、この地域ではまだ松之助という人は日常生活に根ざした、家族の一員のような存在であり、その記憶は連綿と受け継がれています。これには私も驚きました。そういう愛着を持って80年以上にもわたって愛されたスターは、日本映画史の中でも他に存在しなかったのではないかと思いますし、映画の創成期から死してもなおずっとそうした存在であり続けているのも、松之助の功績かと思います。
二つ目は今の人気の話とも関連します。松之助の時代が終わったとされる大正末期から、マキノ映画に代表されるリアルな活劇や大衆小説と連携した時代劇がどんどん作られ始め、そこで初めて大衆小説と時代劇が融合したと言われます。しかし考えてみれば、それ以前の松之助の作品も、大衆小説の先駆けと言われる立川文庫(たつかわぶんこ)や、先ほど児玉先生がおっしゃっていた、雑誌などで読み物としても普及された講談を題材にしていました。つまり、人々に知られていた物語を映画にするという意味と同時に、原作の印刷メディアと映画というメディアの融合はすでに松之助映画でおこなわれていたわけですね。松之助映画の人気にともなって、物語が活字とフィルムの2つの媒体を横断して大量に生産され、大衆の間に浸透し、日本の物語映画の可能性を広げていった、ということも松ちゃんの功績といえるでしょう。
三番目としては、これも若干ローカルな話ですが、先程話したような題材の選定も含めて、時代劇映画を作る撮影所のシステムを築いたことです。一つ具体的な例を出しますと、東映や大映などの時代劇のロケーション地を調査しますと、それらの多くが松之助映画で使われていた場所なのです。ということは結局、松之助が死んでも、松之助映画を作っていたスタッフによって、「こういうシーンを撮るならあそこのロケ地だ」「こういう背景が欲しいのならあの場所だ」という情報が、撮影所、特に戦前の日活京都の撮影所の中でずっと引き継がれていたわけですね。例えば皆さんが多分、よくご覧になっていると思われる光景としては、東海道新幹線で東京から京都の一歩手前まで近づくと、滋賀県の瀬田川という川がありまして、「あみ定」という旅館が見えます。ここは松之助の時代から、そして日活京都でもマキノでも東映でも大映でも、ずっと愛用されていたロケーション時の定宿なのです。そのような、「日本のハリウッド」と言われた京都での映画製作の土台を、松之助と松之助映画が作ったという点も大きな功績かと思います。
以上、“松ちゃん”の功績を3つほど簡単にまとめましたが、さて今日は“松ちゃん”の足跡を京都の中にたどりつつ、その魅力を紹介することをメインの目的にしています。史跡マップを説明する前に2点だけ、今から足跡をたどる“松ちゃん”の特徴を紹介します。
まず、これは一般的にも言われていますが、彼が労働者層を、特に京都では西陣の織工たちを主な観客層とした映画を作り続けてきたということです。低年齢層や織工たちを対象にしていただけに、広く多くの観客を獲得することができた反面、インテリ層からはたくさんの批判も浴びました。批判の中でジレンマを抱きつつも、彼はその路線を変えることは決してありませんでした。なぜ変えなかったのか、変えられなかったのかという点は、つい「松之助のルーツは歌舞伎だから」の一言でくくられてしまいがちなのですが、京都というローカルな視点から見ると、やはりこの町がそうさせたのではないかと考えざるを得ません。今日はそのあたりを説明できればと思います。
もう一つの特徴は、これは松之助の作品歴や活動歴を見て強く感じるのですが、やはり牧野省三との関係の強さです。というのも、松之助作品の作風に違いが出てくるのは、牧野省三が独立して劇映画も作っていくマキノ映画製作所を1923年に立ち上げてからなのです。それまでは、多くの松之助の映画は、いろいろ批判を浴びながらも、忍術ものを中心にしたり、講談などのヒーローを主人公にしてきたのですが、マキノ映画が設立されて、大衆小説的な物語展開の時代劇映画が作られ、阪東妻三郎が登場し、時代劇をめぐる状況がどんどん変わってゆく中で、松之助作品の様相も少しずつ変わってきましたし、また慈善事業など映画以外での活動も加わってきます。そこには牧野省三との表裏一体の関係があるように感じます。もちろん、松竹から伊藤大輔の脚本で新時代劇の作品群が出てきた中で、松之助映画の変化の理由を、マキノ映画と言い切ってしまうのは暴挙かも知れませんが、例えば、講談ものよりも新聞連載の大衆小説を題材にした作品を積極的に発表していくようになるのは、マキノ映画の阪東妻三郎が新スターとして絶大な人気を獲得した頃からです。この頃から日活とマキノの競作映画も作られるようになり、批評家が、「マキノ映画よりも松之助の映画の方が面白いとはどういうことだ」と驚くほど[注1]、内容的にも変わってゆきます。また、「鞍馬天狗」もそうですが、マキノ映画の特徴だった覆面ものを積極的に取り上げたのも、マキノ映画設立以降の松之助映画の特徴と言えます。ともすると「松之助映画には変化がない」と言われてしまいがちなのですが、仔細に見ていくと、常に映画を一緒に作り、一体の関係であった牧野省三がいなくなって、彼が松之助映画に対するアンチテーゼのような作品を作り始めて日本映画界を変えていった時に、松之助も、やはり自分の映画の枠を広げようと試みるのです。ただし、演技のスタイルはあまり変えることがなかったようで、幼い観客層や労働者の人気も保っていたように思います。
図1:“目玉の松ちゃん”史跡マップ(左)/図2:“目玉の松ちゃん”活動マップ(右)
では後はゆっくりこの史跡マップを解説したいと思います。「“目玉の松ちゃん”史跡マップ」と書いてある[図1]を見てください。真ん中が「洛西撮影所図」で、現代の地図に、かつてあった撮影所の位置や松之助の史跡などを書き込みました。撮影所の番号を①から⑬までつけまして、1930年代までに洛西地域に作られた撮影所の位置と順番が分かるように番号を配置しました。但し、⑫の嵐寛プロの位置は、丸つき数字ではなくその上の四角印です。
この地図と併せて見ていただきたいのが、[図2]の白黒地図です。これは1903年の地図で、領域は先の地図とほぼ同じです。1903年はもちろんまだ松之助が映画に出る前で、牧野省三もまだ映画を撮っていません。撮影所と史跡の場所を赤印でいれましたので、[図1]の地図とも対比して見ていただくと一目瞭然かと思いますが、この時点では田畑ばかりなのに、その後松之助映画の人気でガラッと撮影所街に変わってしまいました。どれぐらい撮影所が密集しているかと言いますと、[図1]に縮尺で700メートルを基準線で入れましたのでお分かりいただけると思いますが、非常に狭いエリアに凝縮されています。文献上は、牧野は松之助と袂を分かって大将軍から等持院の撮影所に独立したといった話がありますが、ここも歩いて7、8分の距離です。そういうところで独立云々と言っても、ほとんど分家に近い状態ではないかとすら思えてきます。
史跡を駆け足で説明しますと、[図1]の「洛西撮影所図」の、右端の真ん中辺りにあるAが、松之助の最後の自宅です。そして、その左斜め下にあるBが出世稲荷です。その若干下、2、3分歩いた辺りにあったのが、京都で初めて作られた撮影所と言われる二条城撮影所の跡地です。史跡の写真は昨日の朝、私が自転車で回って撮ってきた映像ですので、日常生活にある史跡として見てください。
まず出世稲荷には、鳥居と向拝新築という、松之助の名前が入った2つの史跡があります。右手の鳥居(1919年奉納)は、左の柱に牧野省三と松之助の名前が入っていまして、右の柱には日活関西撮影所の名前が入っています。向拝新築(1924年奉納)というのは、お参りの時に雨に濡れないように屋根をつけた部分を向拝といいまして、真ん中の下の写真にある、ちょっと飛び出した屋根ですね。これを新築したのが史跡に名前が連なっている松之助と牧野省三と、日活の池永浩久の3名です[注2]。
そして、千本通を上がったところのCが千本座の跡地で、今は「無印良品」(2024年2月現在はドラッグストア)が入っているマンションになっています。松之助が映画に出始めた当時その裏には大超寺というお寺があり、境内で撮影をしていました。千本座の中では芝居をやり、昼間はその裏のお寺で撮影をしていたというエピソードが有名です。次に、Cの下にある中立売通を左に上がると、北野白梅町と書いてあるところにDがあります。これは大将軍(たいしょうぐん)八神社と言いまして、大将軍村の守り神でもある方位よけの神様です。ここには玉垣が寄進されていまして、これは下の文字が埋まっているのでちょっと見にくいのですが、鳥居の右側に3本並んでいるうちのいちばん手前が池永三治、(後に大将軍撮影所の所長になる)池永浩久ですね。その隣は、(横田永之助の甥で大将軍撮影所では会計から理事にもなる)横田豊秋だと思います。そして3本目が尾上松之助です。鳥居の左側には牧野省三の寄進の玉垣があります。
出世稲荷と大将軍八神社の2つの史跡を見ても、常に牧野省三と尾上松之助、また池永浩久は一緒なのですね。袂を分かったと言われますが、向拝新築なども牧野省三がマキノ映画を作って以降のものですし、やはり京都で映画を作ってゆく中で、この3人がいかに連携を保っていたかが分かります。
そして、Dからさらに中立売通を左に進んでいきますと、大将軍(たいしょうぐん)撮影所の跡地があります。分かりやすいように1922年の地図を左上につけておきました。この地図ですと、「大将軍撮影所」の建物が載っています。そしてこの撮影所の右斜め上に四角で囲った、池のようなマークがあるところ、これは松之助の作品のオープンセットを兼ねていたそうです。松之助映画の子役でいらした小林昌典さんに、ここにある4枚の写真を見ながらお話を伺った時、石の形が同じなので、撮影所内のオープンセットですかとお聞きしたところ、「いやいや、それは違う。この斜め前の別荘や」とおっしゃいました。撮影所とは関係ない、本当に単なる近所の豪邸らしいのです。そこには池があって、飛び石があって、建物もいいので、山深いとか庭園とかいうシチュエーションのシーンはよくここで撮影したのだそうです。ですから、撮影所の中だけで撮影が完結していたのではなく、また寺社仏閣の中だけでもなくて、こういった近所の庭も含めて、京都という地域そのものをオープンセット化しながら撮影をしていたという様相の一端がお分かりになるかと思います。
[図2]には、最後にたどり着くべき等持院のお墓を載せました。等持院でもご覧のように牧野省三の銅像とともに、間に立命館大学の建物を挟んで、松之助のお墓があります。松之助のお墓は、銅像の下の写真のように、正面に彼の蝶の家紋が入っています。一番下の写真はこのお墓を裏面から撮った写真で、4基とも全て松之助自身(本名中村鶴三)が作っているのです。大正12(1923)年と13(1924)年に、自分のも含めてお墓を作って、もうこの地に眠るのだと決めています。ですから、単にお墓というだけではなくて、松之助自身が作った史跡としてご紹介しました。
以上、史跡を簡単にめぐってみましたけれども、自転車で走れば1時間ちょっとで済んでしまう距離の中にこれだけ密集しているのです。そしてこの中の、千本通周辺が西陣の興行街です。
ここで、松之助の人気を知るために、[図2]の「“目玉の松ちゃん”活動マップ」の変遷図を見てください。西陣の興行街にあった芝居小屋や映画館をまとめたものです。右上の方の青い四角が繊維関係の工場で、その中の西陣撚糸再整工場は横田万寿之助(稲畑勝太郎と同じ府費留学生としてフランスへ派遣され、紡織技術を学んだ。後に弟の永之助と横田兄弟商会を設立)が重役を務めていた工場でもあります。地図の中央を左右に走っている今出川通の上下には、西陣織の織工たちの町が広がっていまして、そうした工場労働者や織工の人々が過ごす歓楽街として形成されたのが西陣の興行街です。京都には新京極という興行街もありますけれども、そこは学生やインテリ層、有閑層が過ごす場所であって、職人や労働者や子どもたちが行ける身近な興行街は、この西陣でした。
松之助が千本座の人気役者だったというのも、このことに関係しています。松之助は千本座で役者として活躍した後に映画界に入りましたが、その後もなお、西陣の興行街では芝居もやっています。その題目も「石川五右衛門」や「忠臣蔵」といったもので、映画とほぼ同じような題目で、1913年から1917年にかけて特に多くありました。ですからこの京都においては、スクリーンのスターの“松ちゃん”と生で見る“松ちゃん”を同時に楽しめたわけですね。ちなみに、松之助がよく芝居をしていた小屋は、千本座から3本右隣の筋で一条通のそばにあった末広座です。他の芝居小屋でも彼は芝居をしていましたので、地元の西陣でいかに松之助が映画のスターというだけでなく、人気役者として愛されていたかがお分かりになるかと思います。
松之助の活動の足跡をたどってゆくと、その特徴は、牧野省三が独立するまでと独立以降の2つの時代に分かれますが、いちばん注目されていたのは牧野の独立前です。この時代、彼が講談ものなどを中心にして労働者層や子供たちに絶大な人気を保っていた一つの例として、これも松之助映画の偉大さを感じるものですが、1914年から1916年の間に連鎖劇というものが流行ったときのエピソードがあります。
連鎖劇とは芝居と映画をミックスした芝居で、幕が変わったときにどこか有名な地点、例えば熱海の海岸場面などでは、熱海でのロケ撮影映像が上映されるといった芝居です。それで、新京極の興行街を調べてみますと、新京極でも、8割近くが連鎖劇を上演する小屋になるほどの人気がありました。それまでは映画の常設館であっても、流行に乗って連鎖劇を取り入れたり、連鎖劇の代わりに実演と映画を同時にプログラムに組むなど、一種の「実演ブーム」が起きたのです。この連鎖劇の特徴としては、その地域のご当地映像、つまり観光名所になる場所でのロケーション撮影が売りになっていた点があります。それから、派手な滝の場面で水を本当に舞台上に流したり、本物かどうかはわかりませんが、蛇を何百匹と舞台の上に出したりというような、見世物性の強い芝居が人気を呼んでいました。実演を取り入れた常設館でも、奇術やダンスなど見世物性の強いものを見せていたのですが、その新京極で、映画の常設館として牙城を守っていたのが日活の松之助映画の上映館なのです。その館では、実演は入れずに映画のプログラムだけで済ませていましたから、それで経営が成り立っていたことの証左だといえるでしょう。そこから考えると、松之助の人気がいかに強かったかということだけではなく、松之助映画が当時の観客の関心事である観光映像だとか、トリックだとか見世物性の強さをすべて備えており、娯楽として堪能させるだけの特色を持っていた、ということを肯定的に見ることができるんですよね。インテリ層からは批判の対象とされていた、これらの特徴があったからこそ、「実演ブーム」の時にも映画を守り抜けたのではないかと思います。
松之助の作品はあまり残存していなくて非常に残念ですが、これからもまだ出てくる可能性はゼロではありませんし、松之助映画を見直すことで、今まで伝説の人物だった“松ちゃん”を、再評価する機会が今後も出てくるのではないかと思います。駆け足になりましたが、この後上映される作品も、松之助の観光映画の特徴をふんだんに盛り込んだ『弥次喜多 善光寺詣りの巻』というものです。だからといって善光寺しか出ないかというと、とんでもない場所も出てくるという、松之助映画のもう一つの魅力を盛り込んだ作品でもありますので、どうぞお楽しみください。
- 一例をあげると、山本緑葉の『燃ゆる渦巻』評(『キネマ旬報』1924年2月1日号)で、「日活の方が遥かに良かった。(中略)マキノの方に却って所謂松之助式なる語の代表する感じを持って居たのはどうした事であるか。」など。
- 出世稲荷神社は、平成24(2012)年7月に、京都市上京区千本通竹屋町下ルから同市左京区大原に移転し、鳥居と向拝新築の記念碑も同地に移築された。
*肩書はブックレット刊行時(2007年3月)。現職は、国立映画アーカイブ主任研究員。
映画俳優 尾上松之助
小松弘(早稲田大学文学学術院教授)
フィルムセンターから、外国の同時代の俳優と尾上松之助を比較するというテーマをいただきまして、演題も「映画俳優 尾上松之助」としたわけですけれども、さて、考えてみますと、松之助は同じ時代の他の国の俳優と比べることが可能なのか、悩んでしまいました。大体、似ている点、異なる点を考えてみますと、異なる点を挙げるのはたやすいのです。ですから、逆に似ている点を無理にでも考えてみると何か面白いことが分かるのではと思いまして、最初にその点を話してみます。
松之助は、日本における最初の映画スターと言っていいと思います。つまり「松之助以前」と「松之助以降」というのがありますし、松之助以降も長い間、日本映画には他の大スターが不在だったと思います。もちろん、新派においては日活の向島撮影所などにスターは確かにいまして、旧劇の映画については澤村四郎五郎などが天活にはおりましたけれども、やはり松之助の圧倒的な人気には及ばず、松之助以降もなかなか彼をしのぐスターは現れなかったのです。
では、松之助より前はどうだったかというと、松之助が出る前の日本映画の状況としては、確かに俳優たちには名前を知られている者もいました。しかし、大概は一座の名前が代表していたのです。山長一派であるとか曾我廼家一派であるとか、そのような形で出演俳優たちが紹介されることがほとんどだったわけです。
ところが、松之助はすぐにスターになれたわけではないのですが、ある時期にスターになってから、彼の単独の映画が非常に長い間作られていました。こうして「松之助以前」と「松之助以降」を考えますと、まず一人の俳優がスクリーンの前景に出てゆく、つまり映像における一つの存在としてクロース・アップされたという現象があると思うのです。
では、同じような時代に、外国でそういった例があるかどうかを最初に話したいと思います。実はヨーロッパでもアメリカでも、映画の俳優の名前は最初から知られていたわけではありません。比較的長い間、俳優の名前というのは隠されていたのです。特にアメリカの場合には、いろいろな事情があるのですが、1909年ぐらいまでは俳優の名前が全く隠されていました。この1909年というのは、実は松之助が横田商会の映画に出た最初の年です。この年代をちょっと頭に入れておいてください。
ヨーロッパではどうかというと、もう少し早くから映画の俳優が知られるようになりました。しかしながら、それも大体1907年ぐらいからです。最初は映画の中のキャラクターとして、そしてそれがスターになるのですが、そうしてまず認知されたのは、喜劇役者です。つまり、コメディアンは他の映画の俳優と違って、非常に早くからスクリーンの前景に出てきたわけです。それはどうしてかというと、スクリーンの上に出てくるいろいろな人物の中で特異な存在、突拍子もなく変なことをする人というのは、やはり人の目をくぎづけにするものです。
このようにして、1907年ぐらいから、特にフランスを中心として、間もなくイタリアでもできますけれども、映画の題名にスクリーン上のキャラクター名を持ったシリーズが出てきます。例えばアンドレ・デードの「ボワロー」シリーズや、マックス・ランデーの「マックス」シリーズなどです。そういう場合には、「ボワローが何々をする」とか「マックスが何々する」というタイトルになります。そうすると、観客たちも彼らを見たいために映画館に通うようになります。スクリーンの中に無名の人々がたくさん出て芝居をするのではなくて、明らかに単独のスターが前景に出て観客の目を引きつけるということが1907年ぐらいから始まります。アメリカでは少し遅くなりますが、喜劇役者ではなくて普通の俳優が1909年ぐらいから映画のスターになっていく状況がありました。つまり、世界的に見て映画の俳優がスターとして認知され始めるのは大体1907年から1909年ぐらいにかけてといってよいと思います。そして、松之助が映画に出演し始めたのも1909年です。しかしその頃の資料を見ますと、松之助が単独でスターとして見られていたとも限らないのです。
では、世界的にどうしてその頃に映像の前景に俳優たちが出てきたか。あるいは俳優の名前がパブリシティに乗り始めたか。あるいは俳優の名前が映画のポスターに記されたり、俳優の名前自体が映画のタイトルになってきたかと言いますと、それは映画プレスの発展とも関係があります。つまり、世界的に見て1907年ぐらいから、映画の業界紙が出始めてきまして、それらが俳優の名前を一般に告知するようになります。それ以前の段階、映画のプレスがそもそも散発的にしか存在しない段階においてはそういったことはなかったのですが、映画の定期刊行物が出てきますと、俳優の名前がどんどん出てきて一般に知られるようになります。日本の場合も同じでして、日本では1909年以降、映画の雑誌が刊行され始めます。そういった中では俳優たちの名前がはっきりと印刷されて知らされるようになり、それはすなわち、スターを誕生させるきっかけをも作ったのです。
では、松之助は一体いつから人気が出てきたのでしょうか。もちろん松之助の名前は1909年ぐらいから知られていました。しかしながら、特に彼の人気が大きなものになった理由には、映画がサブカルチャー化されていったことと関係があります。つまり、忍術映画が作られ始めたのです。忍術映画というのは大体、立川文庫(たつかわぶんこ)などに取材するのですが、その創刊は1911年でして、これに牧野省三が目をつけます。それまでは歌舞伎や講談、義太夫などを主として、大人が受容する説話文化に根ざした旧劇映画が圧倒的に多かったのです。ところが、立川文庫はもっと若年層に読ませるためのお話でして、牧野省三がこれを続々と映画化し、中でもトリックを使った忍術映画が大ヒットしてゆくのです。
そして、松之助がそういった映画にたくさん出るようになりますと、以前の観客層とは随分違う、子どもたちという観客層ができてきます。つまり、映画館の客層のかなり多くの部分を子どもが占めることによって、映画がある種サブカルチャー化されてゆきますが、それが松之助の人気を大きく支えることになります。子どもたちという新たな観客層を獲得することにより、それ以前の映画の観客とは異なった状況を映画館が形成するようになり、それによって作られた映画の急激な人気の高まりが松之助をスターにした一つの要因ではなかったかと思います。
こうして旧劇映画をサブカルチャー化した中心人物は、もちろん牧野省三でした。しかしよく知られているように、松之助と牧野省三との関係には微妙なものがありますし、また牧野省三というのは非常に倫理的な人物でした。松之助の忍術映画などが子どもに大きな悪影響を及ぼすに至って、自分が作っている映画が社会にマイナスの面をもたらすことに良心の呵責を持つようになります。ですから、その後牧野省三は松之助に対して反発し、日活を出て教育映画を積極的に作ってゆきます。その背景には自らが作った映画のサブカルチャー化に対する良心の呵責があったとも考えられます。
話を松之助に戻しますと、彼がスターであるということは、外国の俳優と比べてやはりかなり特異な意味を持っていると思います。先程言ったように、ヨーロッパで最初に一般の観客に映画の俳優として認識されたのが喜劇の俳優たちであったのに対して、日本においては旧劇の尾上松之助がそういった人物でした。しかし、その喜劇俳優たちと松之助には大きな違いがあります。ご存知のように、この時代の日本にはほとんど喜劇というものがありませんでした。いや、もちろんそれは言い過ぎかもしれません。確かに明治時代の映画のカタログの分類を見てゆきますと「喜劇の部」はあります。しかし、それは新派や旧劇に比べるとはるかに小さく、実写映画よりも数が少ないということも事実ですし、実際大正時代になると、関東大震災の直前まで、日本では映画の喜劇は外国映画でのみ見るものとされるようになります。
つまり、松之助の忍術映画がサブカルチャー化して人気が出てきますと、もはや日活では喜劇を作る余地が全くなくなってしまいまして、現実的にほとんど作られなくなるのです。喜劇は旧劇に統合されてしまうか、もしくは全く排除されるかのどちらかになるのです。新派は悲劇であり、喜劇的な要素を持ち得ないですから、喜劇はあり得ません。かりに喜劇的な要素を持たせるとするならば、旧劇にインテグレートされた形かという気がします。ですから、松之助映画を見ていても、喜劇的な要素がないわけではないのです。残念ながら今回は上映されませんでしたけれども、早稲田大学に1本、松之助の映画でまだ一般に上映されたことがないフィルムがコレクションとしてあるのですが、その中には人を笑わせるような場面も出てくるのです[注1]。それは旧劇にインテグレートされた喜劇的な要素と言えます。ですから、日本におきましては、1911年から1910年代後半ぐらいまで、喜劇は旧劇の中に取り入れられた形でのみ存在したのではないかという仮説を立てることができます。
このように、ヨーロッパの喜劇役者と松之助では全然違います。しかし、スターという点では、チャップリンに似たようなところがないでもない。誤解を受ける言い方かもしれませんが、私は今回、「映画俳優 尾上松之助」という課題を与えられた時、そんなことをふと考えました。どうしてかといいますと、少し実証的に考えてみますと、大正時代にいろいろな映画雑誌が出ましたが、表紙をめくりますと大体まずグラビア写真があります。そこには同時代の映画俳優、スターたちの肖像がいっぱい載っていますが、多くの場合、最初に外国スターが載っていまして、その後に日本の俳優が載っています。これを見ていてふと気がついたのですが、ヨーロッパもアメリカも、外国俳優のポートレートはほとんど胸から上だけです。ところが日本の俳優の場合は、胸から上のものもあるのかもしれませんが、大概の場合は全身です。松之助の肖像も、彼の顔をクロース・アップしたものとか、胸から上のものはあまり記憶にありません。あったとしても、数はそれほど多くないと思います。
これは面白いことではないかと思います。つまり、松之助をはじめとして、ほかの日本の映画俳優たちも大体の場合全身なのですが、胸から上の顔を撮る必要はなかったのか、もしかすると外国の俳優と並べるには堪えられなかったのかも知れませんが、あれほど人気があったのになぜ全身なのだろうかという気がするのです。
それは恐らく、1910年代には、アメリカ映画やヨーロッパ映画を見る人の意識と日本映画を見る人の意識が基本的に違っていて、それがグラビア写真のポートレートにはっきりと反映されているのではないかと思うのです。要するに、ヨーロッパ映画やアメリカ映画の場合は大体、これは文化的な背景もありますけれども、俳優の表情が豊かです。これに対して日本の映画は、旧劇も新派もそうですけれども、表情が硬直している。では、どこで演技をするかというと、結局全身なのです。所作で表現するのです。身振りのコードが重要であって、表情による演技があまり求められていなかったのではないかと思います。それから日本の同時代の映画に、それほど接写のショット、クロース・アップも含めた接写のショットが、皆無ではなかったけれども多くなかったことも原因しているかも知れません。
松之助は“目玉の松ちゃん”ですから、目玉をギョロッと剥いた瞬間のポートレート写真があってもいいと思いますし、もしあったら私は欲しいのですが、どうも見当たりません。ですから、目玉を剥くところも、全身で見得を切る時の、身体の動きを一瞬ストップ状態にする動作なのだと思います。
これは重要なことで、例えば立川文庫で、忍術使いが「九字(くじ)を切る」という言い方があって、九の字を宙に書くと、煙がかかって忍者が消えてしまうという術です。南部僑一郎という批評家は、子どもの時代にこういった映画をよく見ていたそうですが、立川文庫のように、右手でパッパと宙を払った後、左手で右手の人差し指と中指を握り締めて云々と文字にするとよく分かりませんが、松之助の演じた映像で見ると「なるほど、ああいう風にやるのだな」と分かります。そして早速家に帰って、その真似をして忍術ごっこで遊ぶのだそうです。
ですから、松之助の面白いところは、それを様式化したといいますか、立川文庫で文字によって表現されたものをビジュアルな形にして分かりやすく見せたことだと思います。松之助の映画はたくさんあって、そのほとんどは失われてしまったのですが、いろいろな主題はあるにせよ、彼のやることは恐らく似たり寄ったりだと思うのです。それがなぜこれほど伝説的になったのかは、明治末期から大正中期までの日本映画を考える場合に、重要な問題を提供してくれるはずです。ですから、「映画俳優 尾上松之助」という今日の主題は、もっと広いコンテクストにつながってゆく重要な問いに違いありません。
まず、映画をサブカルチャー化したことは決定的な意味を持ってきます。では日活京都のライバル会社であった天活の東京派などはどうであったかというと、天活には松之助とライバル関係にあった澤村四郎五郎がいましたが、あちらは大人の観客をも対象に、しかも子どもでも楽しめるトリックを使った映画を作っていました。ですから、田中純一郎の『日本映画発達史』を読むと、一定の年齢に達した人は松之助の映画をガキの見る映画だとして軽蔑して、どちらかといえば四郎五郎の映画の方がいい、と言っています。それは、まさに映画がどの観客層を対象にして作られたかと重要な関係があると思います。
この後、牧野省三は、先程も言いましたように日活京都を飛び出して教育映画の世界に入ってゆきます。そうすると、日活時代に彼が作った松之助映画とははっきり違う旧劇を作るようになります。それどころか、実は彼は最初にミカド商会という会社を作って、そのときにアドバイザーのようないろいろな人材を入れるのですが、いわゆる官の人を引き寄せるのです。官界を映画に引き寄せることは牧野が意識的に考えていたことでした。大体が、ミカド商会の第1作は内務省指定の記録映画ですから[注2]、はっきり官を利用して、しかも自分の映画を教育的な意味で使ったのです。
それは、よくよく考えると松之助映画へのアンチテーゼであるわけです。それからミカド商会の第2作は現代劇の『都に憧れて』という作品なのですが、これは同時代の新派映画と全然違いまして、はっきりと早すぎたといいますか、現代劇とでもいっていいような、まだほとんど現代劇という言葉がないような時代に現代劇的な要素、つまり新派でない現代の素材を作ろうとしていたのです。
このように、松之助の映画に対するアンチテーゼが次の世代にはっきりと出てくるのですが、松之助は死ぬ直前までずっと映画に出ていました。もちろんある時期から本数は減りますけれども、依然として松之助の映画がヒット作であることは変わりませんでした。
世の中でいろいろな映画に対する批判であるとか、映画に対する改革であるとか、そういったものが唱えられ始めるのが大正7(1918)年から8(1919)年ぐらいです。そういった時代になりますと、もはや松之助映画というのも必然的に変わらざるを得ませんでした。
今日はこの前のプログラムでも、その時代である1921年や1926年の作品を上映しましたし、これからの作品はほぼ最後の、彼が死ぬ直前の映画です。そういった映画を見たと思いますが、これらも実は、必ずしも典型的に松之助の所作を表しているわけではありません。それから1910年から1912年でしょうか、もう少しあとの映像も入っている気がしますが、活弁トーキー版の『忠臣蔵』、これもアクションがそれほど多くありません。アクションがあるのは討ち入りの場面ぐらいでしょうか。典型的な松之助の演技というのはあまり分からないかも知れませんが、旧劇も改革せねばならないという批判の対象になった、典型的な松之助の演技スタイルとはスタティックなものです。
これも誤解を受ける言い方かもしれませんが、彼の動き、アクションというのは一瞬静止するのです。それは彼の殺陣を見るとよく分かります。しかも彼の場合は、カメラに向かって斜めという構図がほとんどありません。その後、震災後に出てくる剣戟映画は、阪東妻三郎や大河内傳次郎もそうですけれども、あえて斜めの構図を意識的に使っています。しかし、松之助の所作は、フィルム自体残っていないものがほとんどではありますが、大体正面か後ろ姿です。ですから彼は、後ろを向いて、両手で化け物や敵を倒した後に、今度はくるっと正面を向いて同じような姿勢で体を動かすのですが、その場合もほとんど姿勢は変えないのです。それどころか、体をくねくねしたりもしません。静止しながら辺りの敵を蹴散らすとか、そういう所作です。それが極めて不自然に見えるのは事実ですが、別の言い方をすると完璧に松之助的な様式美であって、それが実は同時代の松之助ファンをものすごく喜ばせたのです。
つまり、彼はほとんど静寂のうちに相手を、敵を、怪物をやっつけてしまう。そういうことが観客には受けたわけです。現存する映画も、1920年代になってきますと、『豪傑児雷也』に若干そういった傾向は伺えますが、必ずしもそうではなくなります。現存するフィルムの関係で、松之助自身が同時代の松竹の新時代劇などを意識し始めた頃の演技の作品がよく見られているために若干誤解されるのですが、それらが少し松之助の本質とは違っていること、批判を浴びた松之助ではないことは少し頭に入れておいた方がいいでしょう。
結局、松之助の映画は1926年まで作られています。彼が1922から23年ぐらいに作った時代劇あるいは新時代劇などがもっと残っていれば比較できると思うのですが、スチル写真を見ただけでも、明らかに化粧が違いますし、リアリスティックになっていますし、同時代の言説もそういう点を指摘するものが多いのです。ですから、松之助自身もやはり、いつまでも自分の作り上げた様式にこだわることは不可能だと分かってきたと思うのです。それを意識化し始めたのが大体1921年ぐらいです。そして震災を経て1924年ぐらいには相当変わります。ですから、1926年の『忠臣蔵』はそれをよく証言していると思います。
1926年という年は、日本映画の一つの時期が終わった年でもあります。松之助が亡くなり、ほぼ同じ時期に栗原喜三郎が亡くなります。そしてほぼ同じ頃に阪妻がユニバーサルと契約して、阪妻ユニバーサルを設立するのです。こうして、かつての旧劇のトップ俳優が早く亡くなってしまい、そして日本にアメリカナイズされた映画を移植しようとした栗原も消え去ってゆく。もちろん震災後ですから、もはや栗原の活躍する場はほとんどなかったのですが。そして阪妻のような剣戟俳優が、今度はインターナショナルな意味を持った映画を作ろうとしたという時期が1926年の後半です。偶然ではあるけれども、まさにそんな時期に松之助は死んでゆきました。彼がもう少し長く生きていたら、もう日活の重役として映画には出なくなっていたかも知れませんが、どのようなことになっていたのでしょうか。興味は尽きません。
- 早稲田大学演劇博物館所蔵『雷門大火 血染の纏』(1916年)。2017年10月24日、同館の正面舞台を利用した野外上映会において、片岡一郎(弁士)、宮澤やすみ(三味線)、上屋安由美(ピアノ)、田中まさよし(太鼓)による活弁伴奏つきでお披露目上映された。
- 『處女會表彰記念式』。題名の表記は御園京平調査『マキノ映画全作品総目録(改訂版)』(1987年)に拠った。また、本作がミカド商会第一作として、内務省の委託を受け、広島県沼隈郡の処女会を取材した記録映画だった旨や第二作の『都に憧れて』については、マキノ雅広『カツドウ屋一代』(栄光出版社、1968年、復刊『伝記叢書299 カツドウ屋一代』[大空社、1998年])71-75頁「教育映画に乗り出す」を参照した。